たくさんの情報をわかりやすくまとめたいとき、どうしていますか?ノートに書いたり、パソコンでメモを取ったりする人も多いと思います。そんなときにおすすめなのが、Googleの「NotebookLM(ノートブックエルエム)」というツールです。
NotebookLMには「マインドマップ」という機能があります。この機能を使うと、AI(人工知能)が自動で内容を整理して、見やすい図にしてくれます。この記事では、パソコンやAIにくわしくない初心者の方にもわかるように、NotebookLMのマインドマップについて説明します。
NotebookLMってなに?
NotebookLMは、Googleが作った情報整理ツールです。PDFやメモ、ドキュメントなどをアップロードすると、AIがその中身を読んでまとめてくれます。また、質問をすると答えてくれるチャット機能もあります。
その中でも、特に便利なのが「マインドマップ機能」です。これは、テーマを中心にして、そこからつながる情報を枝のように広げてくれる図です。内容を視覚的に見ることができるので、理解しやすくなります。
NotebookLMのマインドマップはどう使うの?
マインドマップの使い方はとてもカンタンです。パソコンやスマホが苦手な方でも、次の手順でできます。
- NotebookLMにログインして、ノートブックを開きます。
- 自分の持っている資料(PDFやメモなど)をアップロードします。
- 画面に出てくる「マインドマップ」というボタンをクリックします。
- 自動で図が作られ、画面上に表示されます。
図はズーム(拡大)したり、スクロール(動かす)したりできます。図の中にある項目をクリックすると、その部分に関する質問ができて、AIが答えてくれます。
どんなときに使うと便利?
マインドマップは、いろいろな場面で使えます。
- 情報を整理したいとき:たとえば、旅行の計画やイベントの準備など、いろんな要素を整理できます。
- 難しい内容を理解したいとき:長い文章やむずかしい話を図で見れば、頭に入りやすくなります。
- 新しいアイデアを考えたいとき:テーマから枝を広げていくことで、アイデアがどんどん出てきます。
文字だけではわかりにくい情報も、マインドマップで見ればすっきり理解できるようになります。
知っておきたい注意点
NotebookLMのマインドマップは便利ですが、いくつかの注意点もあります。
- 図の内容はあとから変更できない:図の中身を手で編集することはできません。直したいときは、もう一度最初から作り直す必要があります。
- 保存は画像形式だけ:できたマインドマップはPNGという画像で保存されます。あとで自由に編集したりはできません。
- AIの内容が少しズレていることもある:AIが自動でまとめるので、ときどき「ちょっと違うかも」と思うような内容になることもあります。
このような理由から、NotebookLMのマインドマップは「まず全体をざっくりつかむため」に使うとよいでしょう。
他のツールと合わせて使うのもアリ
NotebookLMだけでは物足りないと感じたら、ほかのツールも使ってみましょう。以下は、初心者でも比較的使いやすいツールです。
- EdrawMind:マインドマップを自由に編集できます。
- GitMind:インターネットを使って友だちと一緒に編集できます。
- XMind:きれいなデザインで、使いやすいマインドマップが作れます。
NotebookLMで作った図を参考にしながら、これらのツールで「仕上げる」という使い方がおすすめです。
無料版と有料版の違い
NotebookLMには無料で使える「無料版」と、お金を払って使う「有料版(NotebookLM Plus)」があります。マインドマップの機能は、無料版でも使えます。
ただし、たくさん資料をアップしたい人や、たくさん質問したい人には有料版のほうが便利です。まずは無料で使ってみて、必要だと感じたら有料版を検討してみましょう。
NotebookLMをうまく使うためのコツ
NotebookLMをもっと便利に使うには、次のような工夫をしてみましょう。
- いきなり本番で使うのではなく、まずは試しに使ってみる
- AIの出した情報をそのまま信じず、自分の目でも確認する
- ノートや図はあくまで「たたき台(下書き)」として使う
このように使えば、初心者でもAIの助けを借りて効率よく情報をまとめることができます。
これからのNotebookLMに期待!
NotebookLMは、まだまだ発展途中のツールです。これからもっと便利な機能が増えるかもしれません。
- マインドマップを自由に編集できるようになる
- 他の形式(テキストやデータ)で保存できるようになる
- AIにもっと細かく指示を出せるようになる
もし今使ってみて「ちょっと使いにくいな」と思っても、今後のアップデートで良くなる可能性があります。まずは気軽に試してみてください。きっと新しい情報整理の方法に出会えるはずです。
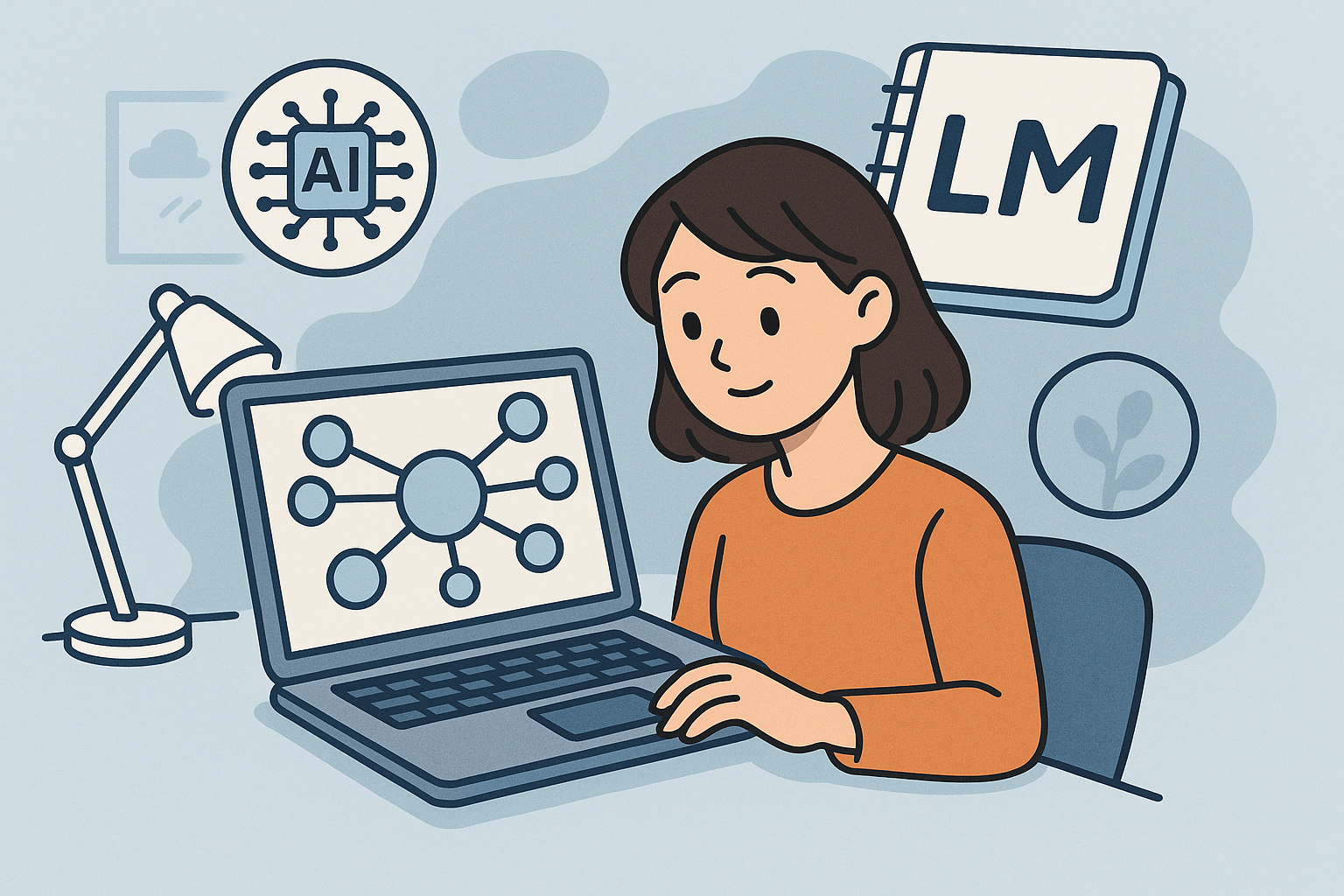


コメント